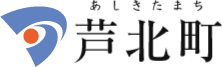国民健康保険税(国保税)について
更新日:2025年04月09日
1. 国民健康保険(国保)とは
病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。原則として、日本国民は何らかの健康保険に入らなければならず(国民皆保険制度)、「国民健康保険(国保)」は勤務先の健康保険に加入していない方や生活保護を受けていない方などが対象となります。
国民健康保険税(国保税)は4月1日の賦課期日で課税されます。国保に加入されている方の前年中の所得金額を基に当該年度の国保税の年間税額を確定して、7月に国保税の納税通知書を送付します。(年度途中で加入された方には、月割計算後、随時、納税通知書を送付します。)
2. 納税義務者について
国保税の納税義務者は世帯主になります。具体的には次の方になります。
- 国保の被保険者である世帯主
- 国保の被保険者でない世帯主であって、同一世帯内に国保の被保険者がいる場合の当該世帯主(=擬制世帯主)ただし、擬制世帯主の所得は税額の計算には含めません(軽減判定時には含みます)。
3. 国保税の計算方法
医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)をそれぞれ計算し、その合計額で課税されます(介護分は40歳から64歳までの方が対象となります)。医療分と支援分はそれぞれ所得割、均等割、平等割の3区分、介護分は所得割、均等割の2区分の合計で決定されます。
所得割の計算で控除されるのは基礎控除(43万円)のみで、所得税や住民税(町県民税)を計算する際の各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)は適用されず、所得金額から基礎控除を差し引いた金額に、所得割額の各税率を乗じて計算します。また、所得税や住民税では免税となる肉用牛の免税所得も含んで計算されます。
なお、純損失の繰越控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除は、所得割額算定の際に控除されます。 しかし、雑損失の繰越控除は適用されません。
<令和7年度の税率等一覧>
| 区分 | 内容 | 税率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | ||
| 所得割 | 前年の所得額から43万円を控除した額に、税率をかけて計算(被保険者ごとに計算し世帯で合計) | 5.9% | 2.00% | 0.85% |
| 均等割 | 被保険者数に応じて計算(一人あたり) | 16,700円 | 5,800円 | 5,500円 |
| 平等割 | 加入世帯にかかる金額(一世帯あたり) | 19,800円 | 7,000円 | ― |
| 賦課限度額 | 各合計の最高税額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
- 国保税は月割計算です。月の末日に加入している保険で賦課されます。そのため、月割で計算した税額と比べてすでに納付いただいた金額が多ければ還付し、不足があれば再計算した納税通知書が届くことになります。転出した後、芦北町と転出先の市区町村から納税通知書が送付されても、二重課税というわけではありません。
(注意)
- 年度途中で40歳になる方は、40歳の誕生日が属する月分から介護分が月割課税されます。
- 年度途中で65歳になる方は、65歳になる月の前月まで介護分が月割課税されます。
- 年度途中で75歳になる方は、75歳になる月の前月まで支援分が月割課税されます。
- 町外から転入された方の国保税については、計算基礎の所得を把握する資料がありませんので、まずは【均等割額+平等割額】を納めていただくことになります。その後に、転入前の市区町村に所得等を照会し、確認でき次第、再計算します。その際、国保税が変更となりましたら、あらためて税額変更通知書を送付します。
4. 低所得者への軽減制度
国保税では、前年の総所得が一定の基準以下(下記の判定方法による)の世帯の場合、均等割額と平等割額の軽減を行っています。
前年の収入が無くても未申告の場合は、所得の判定が出来ないため、軽減制度が適用されません。前年無収入の方も、国保税の申告をしてください。
【7割軽減】
【5割軽減】
【2割軽減】
- 特定同一世帯所属者とは…後期高齢者医療制度の適用により、国保の資格を喪失し、それ以降も継続して同一の世帯に所属する方のこと。軽減判定の際に所得・人数ともカウントされます。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける者をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円を超える者をいいます。また、一定の公的年金等の支給を受ける者とは、公的年金の収入金額が、65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円を超える者をいいます。
(注意)軽減判定時の総所得は以下の点が異なります。
- 未加入の世帯主(擬制世帯主)の所得を含んで判定されます。
- 65歳以上の方の公的年金所得は15万円が控除されます。
- 専従者給与(控除)は世帯主の所得として判定します。
- 土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で判定します。
- 純損失・雑損失の繰越控除は適用して判定します。
5. 非自発的失業者への軽減制度
会社の倒産・解雇、雇い止めにより自己都合によらない非自発的失業者となった方の国保税について、失業から一定期間(離職日の翌日から翌年度末まで、最大2年間)、前年の給与所得を100分の30として計算することにより、国保税を軽減します。
≪対象者≫ 以下の全ての条件に該当する方
- 離職時65歳未満の方
- 雇用保険の失業給付(基本手当)を受ける方
- 雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号が【11・12・21・22・23・31・32・33・34】のいずれかに該当される方
(注)軽減を受けるためには申請が必要です。「雇用保険受給資格者証」、「印鑑」、「被保険者証」(国保加入者)、「マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)」をご持参のうえ、申請ください。
国保を離脱すると終了します。
6. 国保から後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減制度
国保から後期高齢者医療制度への移行により、同一世帯の他の国保加入者が1人だけの世帯(=特定世帯)となる場合、下記の軽減があります。
- 最大5年間、平等割(医療分・支援分)が半額となります。
- 5年経過ののちは、平等割が最大3年間4分の1軽減されます(=特定継続世帯)。
世帯構成に異動があった場合は対象外となります。
7. 被用者保険から後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減制度
75歳以上の方が被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者だった方(=65歳以上75歳未満)が国保加入となる場合(=対象者を旧被扶養者といいます)、下記の軽減があります。
なお、この軽減を受けるためには申請が必要です。
- 所得割が全額減免されます。
- 均等割が半額減免されます(7割・5割軽減を受ける方を除く)。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割が半額減免されます(7割・5割軽減を受ける方を除く)。
- 2、3は資格取得日の属する月以後、2年を経過する月までの間に限ります。
- 旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合、軽減措置は終了します。
- 建設国保や医師国保など国民健康保険法に基づく国保組合は該当しません。
8. 18歳以下の子どもに係る均等割額の減免について
芦北町では”次代を担う子ども”を扶養する子育て世帯支援のため、令和元年度(2019年度)から国民健康保険税の18歳以下の子どもに係る均等割額の減免を実施しています(年齢が満18歳に達する年度の年度末3月31日まで減免)。
詳しいことは「子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減免について」をご確認ください。
9. 納付について
- 国保税の納期(普通徴収)は年8回(7月から11月、1月から3月の毎月)です。便利な口座振替をぜひご利用ください。
- 世帯主を含め被保険者全員が65歳から74歳の世帯は、原則、世帯主の公的年金から天引き(特別徴収)となります。詳しいことは「国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について」をご確認ください。
国保税を滞納すると、短期被保険者証(注1)になったり、滞納処分を受けることがあります。納期内納付にご協力ください。
(注1) 短期被保険者証とは、通常の被保険者証より有効期限の短い被保険者証です。 毎回窓口での更新手続きが必要になります。
関連リンク
お問い合わせ
- お問合せ先
- 税務課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893